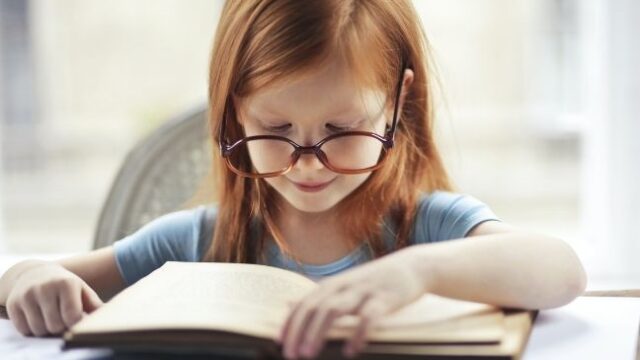最近、外を歩いていてふと気になることがあります。
歩きスマホでふらふらと進む大人。
外食先で、親子そろってスマホを見ながら黙々と食事をする光景。
スマホは便利で、生活に欠かせないツールになったことは間違いありません。
でもその一方で、「今、この瞬間に目を向ける力」が失われているような気がするのです。
だからこそ、私は思います。
「自分の子どもには、画面の中ではなく“いま”を大切にできる子になってほしい」と。
目次
デジタル漬けの時代、子どもも例外ではない
スマホやタブレット、テレビにYouTube…。
子どもたちを取り巻くデジタル環境は、想像以上に過酷です。
気をつけていないと、静かにしてほしい時、手が離せない時…ついスマホを渡してしまうことも。
「少しの時間だけ」と思っていても、気づけば毎日のルーティンになっていた、という家庭も少なくないはずです。
私もそんな一人でした。
わが家で感じた「これはまずいかも」という違和感
ある日、子どもが動画の時間になると声をかけても動画に夢中で全くの無反応になることに気づきました。
身体だけがあって、意識は完全にどこか遠くにいる
終わりのタイミングで泣いたり怒ったりすることが増えて、
「このままでいいのかな?」と不安に。
また、画面を見ている時間が長い日は、
- 一人遊びが続かない
- 睡眠の質が悪い(寝つきが遅くなる)
- 食事に集中できない
- 怒りっぽい
など、明らかに生活全体に影響していると感じました。
以前、話題になったアンディ・ハンセンという精神科医の先生が書いた「スマホ脳」という本では、私たちの脳は原始時代から実はほとんど進化していないと書いていました。
目まぐるしく進化していくデジタル社会ですが、実は私たちの脳は現代のスマホを中心とした生活には適応できておらず、上にあがった4つの事はスマホからの悪影響が顕著に出ているとも言えます。
iPhoneを生み出したAppleの創業者のスティーブン・ジョブズも、自分の子供には14歳になるまでスマホを持たさずにいた事、スマホを持つようになった後も使用を厳しく制限していた事は有名な話ですよね。
無理なく始めた「ゆるデジタルデトックス」
本格的な「デジタル禁止!」を始めたわけではありません。
わが家で実践したのは、“できるところから”のゆるデジタルデトックス。
たとえば──
- デジタル機器を使うのは1日1回など時間を決める
- スマホやタブレットは親の目の届く場所でのみ使用
- 「見せる前提」ではなく、「一緒に遊べること」を探す時間を確保する
この3つをルールとして、無理なく取り入れていきました。
デジタルから離れて見えてきた“本当の楽しさ”
ルールを始めてすぐ、子どもに変化がありました。
最初は「YouTube!」とぐずった日もありましたが、
次第にその時間を、ブロック遊び、絵本、簡単なお手伝いなどに自然と置き換えていくように。
何より驚いたのは、自らテレビを消して、「一緒に○○しよう!」と誘ってくれるように鳴った事。
ぬりえやブロック遊び、料理を一緒にすることも、楽しい「遊び」に変わりました。
“目の前の世界”をしっかり味わっている様子を見て、安心したのを今でも覚えています。
デジタルデトックスで気づいた、親の“スマホ依存”
実は一番難しかったのは、親である私自身のスマホとの付き合い方。
無意識に手が伸びてしまうSNSや無意味なネットサーフィン。
子どもに「スマホばかり見ないで」と言いながら、自分がスマホばかり見ていたら子供への注意に説得力なんてありもしませんよね。
そこで思い切って「一緒に過ごす時間はスマホを触らない」を私のルールに。
親の姿勢をマネするならばと、、ちょっとした手の空いた時間に今まで持っていたスマホを”本”や”楽器”に変えました。
親をマネしてスマホをいじるならば、親をマネして本を読む習慣を身につけたり、楽器を弾けるようになれた方が圧倒的に良いですよね。
私はギターを弾いているのですが、弾いていると娘はその横でピアノのおもちゃを弾いて、簡単なセッションが始まります。
私自身、デジタルデトックスを意識し始めてから、睡眠の質があがったり、SNSで変に感情が動いて疲れたりなどすることが激減しました。
まだ完ぺきにできているわけではありませんが、すこしずつデジタルデトックスの時間を増やしていけたらと思っています。
完璧を目指さない、でも“今を生きる”力を育てたい
デジタルを完全に排除するのは、現実的ではありません。
でも、子どもの生活の中に「デジタルがなくても心地よい時間」を少しずつ増やしていくことで、
“今この瞬間”を大切にする力が自然と育っていくのではないかと感じています。
「いま、ここにいる」を味わえる子に。
それは、これからのデジタル社会を生きるうえで、最大の武器になるかもしれません。
これからの時代、デジタルを“使いこなす力”も育てたい
デジタルデトックスを意識する一方で、私は最近こうも感じています。
「これからの時代、完全にデジタルから切り離して育てることは現実的ではない」
むしろ、子どもたちは大人になる頃には私たち以上にテクノロジーと密接に関わる社会を生きることになるでしょう。
そう考えると、大切なのは「使わせない」ではなく、「どう使うか」「どんな目的で使うか」を学ばせることなのかもしれません。
例えば、四六時中スマホを手放せないスマホ依存症の人は、スマホに支配されているような状態です。
デジタルに支配されるのではなく、使いこなす力を身につけていくのが大事だとも考えています。
たとえば、
- 動画をただ見るだけでなく、感想を話す習慣をつける
- 家族で使うときは、「〇〇のために見る」という目的を共有する
- 一緒に調べものをする、地図アプリでお出かけ先を選ぶなど、ツールとして体験的に活用する
こういった「親子でデジタルリテラシーを育てていく」関わり方なら、子どもにとってもストレスが少なく、自然にデジタルとの上手な距離感が身についていく気がしています。
まとめ
デジタルデトックスというと難しく聞こえるかもしれませんが、
大切なのは“ゼロにすること”ではなく、“どう付き合っていくか”。
私たち親が、まず自分の行動を見つめ直すことから、
子どもの健やかな生活リズムと心の安定につながっていくと信じています。
「デジタルに支配されない子育て」を目指して──
わが家の取り組みは、これからも“ゆるく、でもしっかりと”続いていきます。